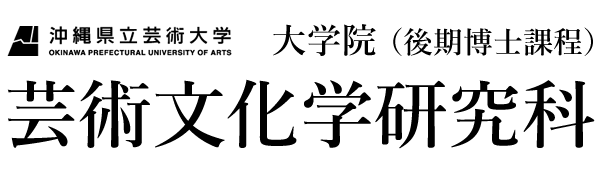博士論文要旨
本論は、東松照明が「写真を組む」方法として提唱し、実践した「群写真」という方法論の変遷から、その意義を明らかにすることで、戦後日本写真史における東松の位置付けを明確にする試みである。対象とするのは、写真集の刊行を活動の主軸とした1990年代末までの作品である。写真集に注目することは時代や主題ごとに形式を更新してきた「群写真」の比較検討にとっても有意義であると考える。
「群写真」は、複数の写真を一見してアトランダムな「群れ」として提示する手法である。この手法が目指すのは、個々の写真がもつ個別的な情報や意味内容を相互的に掛け合わせてゆくことで、新たなる意味の発生を促しつつ、写真相互の結合を網目状に展開させることである。このような発想は、戦前から戦中にかけて隆盛を極めた「報道写真」における写真の組み方――複数の写真と文章を一方向的な物語に沿うように並べ、そのままに読み手に読解させる「組写真」に対する批判に由来している。写真家の定めた正解にむけて読者を誘う組写真に対して、「群写真」は、複数の写真のさまざまな関係性から不可避に生じる恣意的な意味の読み取りを鑑賞者に許すことで、写真群を自由に「読んでいる」という幻想を抱かせつつ、その果てで、どうしても読み取り得ない残滓に気づかせ、そうすることによって「全体の方向性」を、いわば、ひとつの場として表象する編集技法である。
本論では、この場としての「全体の方向性」を、各写真集における個別的なテーマを表象することにのみ寄与するものではなく、その背後に見え隠れする「戦後日本」や「原初的な日本」の影、そして、その集合体であるところの「日本‐国家」の不明瞭かつ流動的な境域へと視線をいざなうベクトルと解釈する。いいかえれば、群写真とは、日本国を「群」として捉え返すためのレトリックなのである。
「群写真」に関する先行研究では、1960年代の初期作品が分析の対象とされてきたが、60年代末期以降には、先行研究の成果だけでは十分に説明がつかない作品が数多く存在する。
たとえば東松が初めて沖縄を訪れた年に刊行された写真集『OKINAWA沖縄OKINAWA』(1969年)に見出される説明的な告発文章と沖縄闘争を中心にした当時の沖縄の現状を写した写真との並置は、形式上、まさに組写真様のものでありながらも、興味深いことに東松は、この写真集を「群写真」を説明するために最も適当な好例として紹介しているのだ。見方によっては名取的な組写真ともみられかねない本書を以て「群写真」の好例とする東松の見方は、この写真集が、「群写真」の展開を踏み込んで検証するうえで重要な鍵となるものであることを物語っている。
また、70年代の『太陽の鉛筆』(1975年)や『光る風―沖縄』(1979年)などの沖縄・先島諸島から東南アジアまでの連なりを視野に入れ、群島の島嶼性を写真集に表象する試みは、沖縄が直面する現実を擬似現実へと改変させて拡散する暴力的な方法であるとして、今なお批判を受ける対象となっているが、そうした批判の存在は、自由な読みを許すことで「全体の方向性」に気づかせる「群写真」の意義をアイロニカルに証明する決定的な事例であったということもできるだろう。
1980年代の丸10年を費やして撮り続けた桜をまとめた『さくら・桜・サクラ』(1990年)は、一般に「日本」的なるものへの回帰として語られることが多いが、沖縄や東南アジアに日本の古層を見出そうとした東松の眼差しが桜や京都という主題へと向いたことは至極自然なことであり、そうであるとすれば本書は、70年代の沖縄という主題との連続性のなかでこそ捉えられるべき作品ではないかと考えられる。さらに、本書で述べられた「集合の美」ゆえに桜は美しいという東松の言表は、「群写真」を「星雲状の塊」あるいは「マッス」と表現したこととも連関づけられるゆえに、80年代における「群写真」の展開を示す重要な指標となる。
90年代の主だった作品には、60年代の初期作品からの連続性が強く見出される。60年代に「群写真」と併せて相互補強的に用いられた「インターフェイス(境界)」概念に基づいて、海と陸地との境界地帯を撮影した〈潮間帯〉(1966年)や、絵画的構図の〈アスファルト〉(1960年)からの展開として、被写体を変えてカラーで写された《プラスチックス》(1988−89年)、《キャラクター・P》(1996−98年)など、60年代作品からの展開を示す作品が多数制作されており、年代を越えた作品の類似的な連なりがそこに見出される。
以上に示したような、およそ60年代から90年代までの東松の具体的な仕事を、まさに「群」の如くネットワークとして捉え返すことで、「群写真」が如何なる変遷を辿り、更新されてきたのかを検証し、「群写真」の新たな見取り図を提示する。
博士論文英文要旨
Theory of “Gun-shashin”–Tomatsu Shomei’s Methods and Thoughts
The purpose of this study is to clarify the position of Shomei Tomatsu in the postwar history of Japanese photography by tracing the transition of the “Gun-shashin” methodology that he advocated and practiced as a way of “combining photographs,” and by clarifying its significance. The subjects of analysis In this study are his major photobooks published until the end of the 1990s.
The “Gun-shashin” as an editorial technique for photobooks creates new meanings by “cross-fertilizing” photographs that have individual meanings. This idea stems from criticism of “Photo-essay” in Photojournalism, which flourished before and during World War II, in which photographs and text were arranged according to a predetermined story. In contrast to “photo-essay,” which allow the reader to interpret the meaning as intended by the photographer (editor), “Gun–shasin” is an editing technique that creates a direction of meaning for the photobook as a whole by allowing the reader to read arbitrary meanings that inevitably arise from the relationships among the photographs, and by creating the illusion that the reader is reading the photographs ‘freely’.
The meaning of the photobook as a whole not only contributes to the expression of the individual themes of each photobook, but is also a vector that invites the reader’s gaze into the shadows of “primitive Japan” and “postwar Japan,” and the ambiguous and fluid boundaries of “Japan-nation” as a totality of these images. In other words, “Gun-shashin” is a rhetoric to recapture the nation of Japan as a kind of “herd/group/flock, etc.”.
Based on the above perspectives, this study presents a new view of “Gun-shashin” by examining how “Gun-shashin” has changed and been renewed.
論文審査の結果の要旨
本論文は、戦後の日本の写真界を代表する人物の一人である東松照明について、キャリアの出発点となるリアリズムへの覚醒から描き起こし、主要な写真集の数々を取り上げて細部に立ち入った考察を加えたものである。この、真意を決して単純には語らない複雑な写真家が自らの指針とした、制作に通底する方法もしくは思考として、「群写真」という概念を提起し、そうした一貫した方法論の発展を辿りつつ、晩年の制作にまで至るなかのさまざまな試みの断絶と連続の錯綜を解き明かした。もとより「群写真」という概念は、「組写真」を標榜する名取洋之助との応酬のなかで東松がこれに対抗するかたちで打ち出したものであるが、本論文はそれを東松の長いキャリアを貫く広い文脈を規定するものとして捉えなおしたのである。
第一章においては、東松のリアリズムの形成を「群写真」および〈インターフェース〉というキーワードを手がかりに辿られている。初期のキャリアで培われ確立した東松独自のアプローチが、彼が「群写真」を示す好例として挙げる『OKINAWA 沖縄 OKINAWA』へと引き継がれてゆくまでが解き明かされている。
第二章においては、東松と沖縄のかかわりについて考究されている。『太陽の鉛筆』、『光る風、沖縄』、『朱もどろの華』という、沖縄をテーマとした写真集を取り上げてその取材の様子なども確認しながら、東松と沖縄のアンヴィヴァレントな関係が論じられている。
第三章では、沖縄での経験を経たあとに繰り広げられた80年代から90年代の仕事が論じられている。『さくら・桜・サクラ』をはじめとした諸作品が取り上げられ、群写真が「原日本」へと迫っていく様子が「混在郷」(エテロトピー、ヘテロトピア)という概念を手がかりに考察されている。
こうした一連の考究は、執筆者が長期にわたる調査や論述を積み重ねてきた成果であるが、一方で、審査員からは、わずかに言及のあるJ-L. ゴダールの映画論との関連をそれ以降の記述に活かす可能性があり得たのではないか、東松の内在的な原理や創作に集中するあまり同時代の写真家たちとの比較の視点が弱い、沖縄近代史の重要な事件との関係づけがいささかもの足りない、群写真にとってむしろ好都合であるはずの、展覧会形式という発表形態についての言及が欲しい、などの指摘があった。また、形式面での様々な不備が指摘された。
しかしながら、本論文は先行研究に増して包括的な視点で東松照明の独自な写真表現を照らし出したものであり、東松照明の写真の研究、さらには戦後写真史の研究に十分に貢献できるものであると評価できる。
最終試験結果
最終試験(口述)(日時:6月7日16:30~18:10 場所:一般教育棟3階302教室)
初めに申請者によるプレゼンテーションがおこなわれ、それを受けつつ提出論文の内容および関連する事柄についての質疑応答を実施した結果、ほぼ全般にわたって的確な返答が得られ、申請者の見識を確認することができた。
総合判定
審査委員会は審査にあたり、「沖縄県立芸術大学大学院芸術文化学研究科(課程博士)博士論文等審査基準」に従って形式的要件を確認し、評価基準をもとに評価を行った。形式的要件は十分に満たしていると判断した。成績については、100点満点中85点以上を合格とすることが確認された。合議の結果、論文及び最終試験ともに合格点を超える成績となったため、総合判定は合格とした。