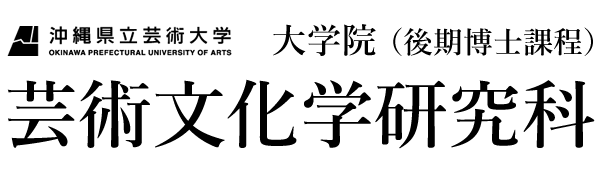博士論文要旨
本論は、近代日本画のリアリズムを分析し、そこから現代のリアリズムの在るべき姿を考えることを目的としている。本論が検討したリアリズムとは、画家と自然との関係性、つまり絵画芸術が自然(現実の現象)の模倣を行う際の、目的意識の在り方のことを指す。近代絵画は自律性を重んじて自然を離れ、抽象表現へと突き進んだが、それでも21世紀の我々は、自然を絵に描き続けている。今日においても、自然の模倣は絵の基本であり、それは画家が絵を描く動機と直接関わる、大切な問題だ。
日本画においてこの問題を考える為には、まず近代日本画におけるリアリズムの変遷を俯瞰することが必要となる。近代日本画を通史的に読む研究には、比較的新しいものが既に沢山ある。またリアリズムの観点からは、西洋絵画史を分析したものや、近代文学について述べた研究もある。しかし、近代日本画をリアリズムの観点から通史的に研究したものは見当たらない。そこで本論は、リアリズムというテーマに合わせて複数人の近代日本画家の画業を分析し、更にそれを前提として、今日の日本画家が自然に対してどう向き合うべきかを考察するという、大きく2つの作業を行うものである。
前者の作業については、第一章から第五章にかけて行った。ここでは舶来のリアリズムとしての「写実」と東洋画の伝統としての「写生」を区別し、近代日本画史において「写生」が「写実」の理論に合わせて読み替えられていく過程を分析した。具体的には、日本画の黎明期である19世紀末から、日本画滅亡論が取り沙汰される戦後までを5つの章に分割し、それぞれの章で1人ずつ、合計5人の日本画家(竹内栖鳳、小野竹喬、平福百穂、福田平八郎、東山魁夷)を中心的に取り上げた。
まず第一章と第二章では、写生派の系譜の近代日本画家が「写実」を内面化していく様子について述べている。第一章では、京都写生派の竹内栖鳳が、洋画の「写実」へと合流し、風景画を描く様になるまでの過程を述べた。第二章では、栖鳳の弟子である小野竹喬を中心として、風景画の視覚形式を内面化した彼が自然の中に風景を発見し、それを近代的な個性の表現として描き始める様子について述べた。
次に第三章と第四章では、上に述べた個性の表現としてのリアリズムが、日本画の伝統との間に生じさせた葛藤について述べている。第三章では、平福百穂の「写生」主義によって、「写生」が日本画の伝統的スタイルとして理論武装されるまでを述べた。ただしここでいう「写生」とは、既に「写実」を通して近代的に再解釈されたものである。更に第四章では、そうした近代的「写生」の両義性によって、福田平八郎の画業が個性と伝統との間で板挟みになる様子について述べた。
最後に第五章では、そうして戦前までに形成された「写生」の理論が、戦後に失われていく理由について考察した。ここで戦後日本画家としてとりあげた東山魁夷の洋風化した風景画は、近代日本画のリアリズムの本質が、洋画の「写実」であったことを物語るものである。
後者の作業については、結論にて行った。ここでは第五章までに分析した近代日本画におけるリアリズムの変遷を総括しつつ、それを田中一村との比較によって相対化し、一村の現代性について述べている。
まず、第五章までに述べた近代日本画のリアリズムは、洋画のリアリズムを通して再解釈された「写実」の亜種としての「写生」であり、それは感覚的、感性的な性格によって、画家の個性の表現として機能していた。しかし21世紀においては、様々な視覚メディアの発達によって、画家の肉眼から特権的な地位が失われつつある。そんな現代に、感覚主義的な近代の「写生」はそぐわない。
対して一村のリアリズムは、そうした個性の表現としての「写生」から脱して、描かれる自然の側の「生を写す」為のものとなった。そこで本論は、21世紀においてもリアリズムを目的として持ち続けたいならば、田中一村のリアリズムが有効であると結論付ける。
博士論文英文要旨
The transition of Realism in Modern Japanese Painting and Its Potential Today : Focusing on the Perspective of Shasei
This study analyzes realism in modern Japanese painting and considers its current ideal form. Realism, here, refers to the nature of the objective in depiction of life in pictorial arts. Modern paintings have emphasized autonomy, abandoning nature behind and moving towards abstraction. However, the depiction of nature remains fundamental to painting, and continues to motivate the artist. To consider this issue in Japanese painting, it is first necessary to understand the transition of realism in modern Japanese painting. There have been studies of the history of modern Japanese painting and of western art from the pespective of realism. However, the researcher has not found any study of the history of modern Japanese painting from the realism perspective. Therefore, this study aims to advance research in two areas, by analyzing the works of several modern Japanese painters from the viewpoint of realism and, subsequently, examining how contemporary Japanese painters should deal with nature.
The first part is covered in Chapters 1 through 5. Here we distinguish between “realism” as in its Western form and shasei (drawing from life) as a tradition in Oriental painting, and analyze the process by which the latter is reinterpreted as “realism” in the history of modern Japanese painting. Specifically, this research is divided into five chapters, i.e., from the beginning of Japanese painting at the end of the 19th century to the post-war period where its decline is discussed, each chapter focusing on one painter. Chapters 1 and 2 describe the internalization of “realism” by modern Japanese painters in the shasei school. The first chapter examines how Seiho Takeuchi of Kyoto merged “realism” into western-style painting and began to paint landscapes. Chapter 2 shows how Chikkyo Ono, a student of Seiho, discovered landscape in nature by internalizing the visual form of landscape painting and began to paint it as an expression of his modern individuality. Chapters 3 and 4 reveal the conflict between realism as an expression of individualism and traditional Japanese painting. Chapter 3 deals with how Hyakusui Hirafuku’s shasei principle led to its positioning as a traditional style of Japanese painting. Shasei here denotes those works that have been reinterpreted in the modern sense through the lens of “realism”. Chapter 4 explains how the ambivalence of such shasei traps Heihachiro Hukuda’s paintings between individuality and tradition. Chapter 5 describes why the prewar theory of shasei was lost after the war. The postwar Japanese painter Kaii Higashiyama focused on westernized landscapes, indicating that the essence of realism in modern Japanese painting was indeed that of Western painting.
The second area of research is described in the concluding chapter. This section summarizes the transition of realism in modern Japanese painting and compares it with Isson Tanaka’s realism in relativizing modern realism. It sheds light on Isson’s realism as de-modernization. The realism of modern Japanese painting as analyzed up to Chapter 5 was shasei as a subspecies of “realism” reinterpreted through the realism of Western painting; it rather functioned as an expression of individuality by reflecting the sense and sensibility of the painter. Today, however, the development of various visual media is eroding the privileged status of the painter’s inner eye. Such sensualistic modern shasei does not find a place in the 21st century. By contrast, Isson’s realism ceased to be shasei as an expression of individualism, and he began to draw life simply as depiction, as the subject is observed. Therefore, this study concludes that Isson’s type of realism is effective in maintaining realism as an objective in the 21st century.
論文審査の結果の要旨
「近代日本画におけるリアリズムの変遷と今日的可能性 「写生」の観点を中心に」と題された本論文は、極めて意欲的なテーマに取り組んだものとなっている。本論文は、「リアリズム」、「写生」、「写実」といった、それぞれ隣接する概念ではあるものの、画家たちによって概念の把握の微細に異なる点を、近代初期から戦後に至る日本画家たちの作品や言説から掬い取り、それらがいかに変遷し、推移してきたのかを丁寧に述べている。
第1章では、アーネスト・フェノロサの近代的な絵画観から影響を受けた竹内栖鳳を取り上げ、栖鳳が系譜的に属する、日本の近代以前の「写実」的とされる円山・四条派の伝統といかに接したのかが述べられる。
第2章では、国画創作協会の構成員、とりわけ小野竹喬における、美術史家・中井宗太郎を経由したセザンヌら「後期印象派」の絵画観の受容が、いかに竹喬の「風景」観を形成し、その写実の実践が具体的にどのように作品に反響したのかを、竹喬の画風の変遷とともに追跡されている。
第3章では、无声会の構成メンバーであった平福百穂が中心的に取り上げられ、自ら俳人でもあった百穂のアララギ派の写生論からの影響や、百穂の故郷で近代以前に展開された秋田蘭画の百穂自身による研究が、いかに百穂のリアリズム観を形成したのかが述べられる。
第4章では、福田平八郎を中心的に扱い、リアリズムの実現と、福田が特徴とする装飾性の伝統とが、いかに葛藤を起こしたのかを述べつつも、その比較対象として、川端龍子の作品が比較される。
第5章では、東山魁夷の戦後の活動が中心に述べられ、近代初期から太平洋戦争に至るまでの間に、様々な日本画家たちによって取り組まれた「リアリズム」、「写生」、「写実」といった取り組みが、いかに変質し、頓挫したのかが述べられる。このようなアポリアに対して、結章において、田中一村の奄美移住後の作例が取り上げられ、日本画というジャンルの、歴史上において等閑視された、一村に特殊な「リアリズム」的実践にこそ、今日の日本画が取り組むべき現代的可能性があるのではないか、との仮説が提起され、論文全体が結ばれている。
このように、網羅的ではないにせよ、概ね編年的に、「リアリズム」、「写生」、「写実」といった概念をめぐって、それらが絵画の実践において顕著に見て取れる画家たちの作品を子細に分析し、言説的な裏付けを比較検討するという、非常に意欲的な論文である。実作者でもある白砂氏は、本論において自作について言及することは行っていないものの、氏が現在取り組んでいる制作の実践を歴史的に検証するという点において、実作品と本論は主題上において緊密に結びついており、同時に、本論が単独の論文としても読むに値するだけの質を兼ね備えているという点において、氏の研究者としての資質も十分窺える。
勿論、上述したような具体的に分析対象とされた画家たちの選択に、幾分かの恣意性が皆無であるとは言えないし、加えて、没後に社会的評価を獲得した田中一村を称揚するという、歴史叙述上の飛躍も指摘できるが、そうした疑問点を上回る重厚かつ論理的に明晰な論述に、本論文は貫かれており、さらには、個別的な作品分析の的確かつ説得力のある論述は、稀有な特質をあらわしてもおり、学位申請論文として高い質を備えていると判断する。
以上のことから、本論文は、「博士論文の評価基準」に照らして、基準を十分に満たしているものと評価する。
作品審査結果
学位審査展覧会(会期;6月3日(金)~6月7日(火)、場所;附属図書・芸術資料館第1展示室)に提出された研究作品を対象に、6月5日(日)に審査を行った。作品展示は大作を中心の芸術表現作品8点について、作品を時系列に展示し整理し解説文を加えて展示発表を行っている。
本作品の始めとして「ロマン」をキーワードとした時代、2017年~2019年の作品《家路》、《海の訪れ》、《光、シーラカンス》、《睡眠、マッコウクジラ》4点は、論文序論と論文第1章より第2章まで論じた内容の実践を含む内容で、論文の早期の内容を含む重要な作品として論文資料と成りえている作品と考える。この4点の大作の作品は論文の近代美術における基礎的な知識を示すに若干欠く面は有るものの、海洋生物をメインモチーフとしつつ、ロマンティックな表現を目的に壮大で神秘的な絵画表現を日本画作品に取り入れた作品である。この4点の作品の表現研究技法の特色として、各作品の日本画における様々な表現技法として、モダンテクニックを独自の材料表現技法として用いて、日本画における海洋生物画として「写実」を主に追求した具象の先駆的な研究作品といえると考える。2020年から作品のテーマを「ロマン」から「風景」へと移行し、本作品の大作《ミュージアム/ヒウチダイ、カガミダイ》は論文第3章以降の内容を実践しており、現実の自然の観察に立脚し「写実」をテーマにした「写生」を追求する作風と創造的空間の追求へと移行した内容を実践した大作である。2021年の大作《興奮暗化するロクセンスズメダイ》は独自の筆法を体得した美しい線描を含んだ日本画の「写実」をテーマにした論文第4章以降を実践した作品である。この作品は高度な薄塗の顔彩の使用した彩色と岩絵具の独自の材料技法による色彩表現や写実表現は特筆すべき新な「写生」内容の作品である。2022年の本年度研究作品の《流れ藻にナンヨウツバメウオ》と大作の《群生するオハグロガキ》は論文の結果にあたる内容の「現代におけるリアリズム」との整合性を強く意識した構想と研究の一体性が強く感じられる作品である。これらの作品は「自然の生命感の発露」とした日本画の海洋生物画の新たな「写生」観を持つ精神的深化と絵画観を追求する画風の作品である。
これら学位審査展覧会における芸術表現作品8点は、学位申請論文と密接に関連しており、各章の論考と論証が整合性をもって表現研究されている作品と考える。これら8点の作品は日本画における技法の習熟度の高さを示し、研究が十分になされた高度な完成度を持つ作品であると判断した。
芸術表現研究の全般について、東京都美術館を会場とし大型作品を対象とする公募展への出品を含めた制作発表と制作活動を精力的に続けて行っている。作品発表は作品の高度な完成度と共に十分な外部評価を受けており、作品の質と量においても十分であることを評価し、作品提出の要件である外部作品発表実績を確認した。
以上のことから学位審査展覧会に提出された研究作品8点において、作品内容及び芸術表現研究の成果として博士の学位の授与にふさわしい質と量を示す芸術表現研究であると評価し、「研究作品の評価基準」に照らして基準等を満たすものと評価する。
最終試験結果
最終試験(口述)(日時:6月5日 13:30〜16:15 オンライン(Zoom)で開催)では、申請者に対して学位申請論文及び研究作品を中心に質疑応答を行い、論文・作品全般を通した総合的実力が確認され、審査の結果合格とした。
総合審査結果
論文等審査委員会は、審査にあたり芸術文化学研究科博士論文等審査基準に基づいて、提出された論文及び作品が各提出要件を満たしていることを確認し、論文・作品・最終試験の成績素点は各100点満点で85点以上を合格とすることとした。提出された論文を「博士論文の評価基準」に沿って審査した結果、基準を十分に満たしており、研究テーマを丁寧に論述されていることを確認した。同じく作品においても「研究作品の評価基準」に沿って審査し、基準を十分に満たしていることが確認された。論文・作品の審査後に行われた最終試験(口述)では、申請者の研究に対する意欲、誠実な研究姿勢が窺いとれ、総合的な実力を確認した。
本論文等審査委員会は、各委員から提出された素点を集計した結果、論文・作品・最終試験の各成績が合格であることから、総合判定を合格と判定した。